連載3-33、日本鳩レース界の歴史
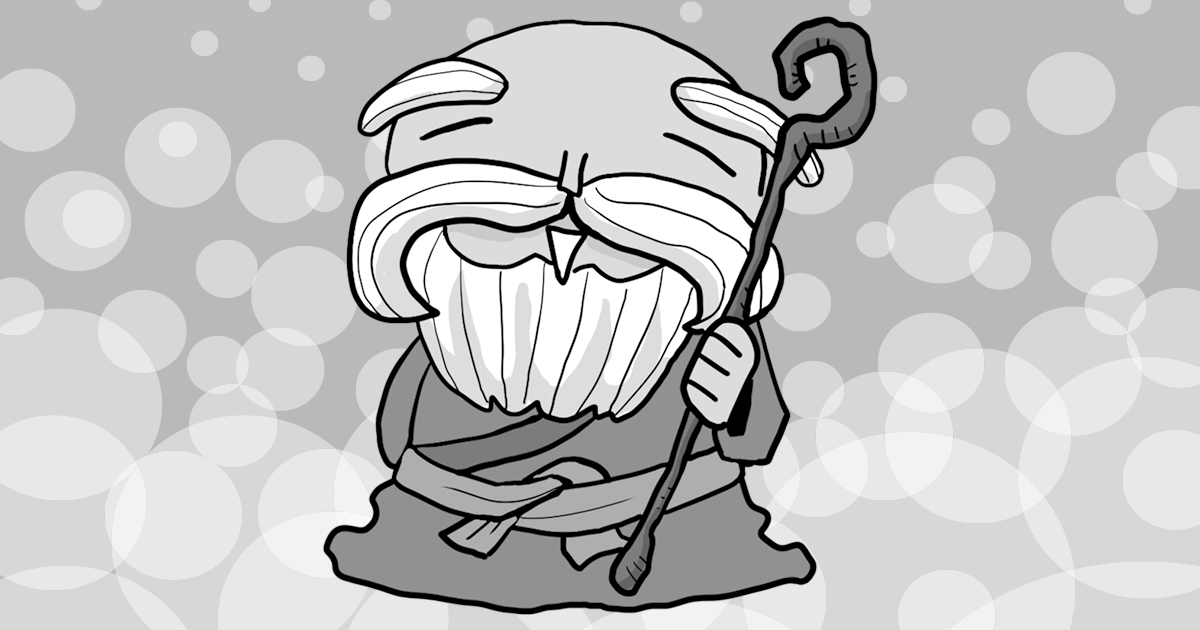
国内への渡来 その十七
さて、徳川幕府の時代、欧米などとの交流は、長崎の「出島」のみになったという話じゃったのう。
日本の資料で、初めてハト通信らしい鳩が姿を現すのは、実はこの「出島」にあったオランダ商館だったのじゃ。
江戸時代も、一般的に通信用のハトの飼育は禁止されておった。それが、一七世紀半ばに描かれたといわれる「長崎出島絵図」の一枚、オランダ商館の庭に、はっきりとわかる二つの鳩小屋があるのじゃ。平戸にあったオランダ商館が、長崎出島に移されたのは、一六四一年であるから、それ以後の物であろう。
では、そこには、どんな鳩が飼われていたのじゃろうか?それは、その頃のヨーロッパでの改良過程を見れば、想像がつくのう。
当時は、一五〇〇年代後半に、イギリスで完成したイングリッシュキャリヤー種と一六〇〇年代に作られたドラゴン種との二種が全盛を誇っていた時代となる。体形的には、原鳩ペルシャと現代の鳩との中間型であって、かなり優れた性能を持つに至っておるのじゃ。
一六〇〇年代の中期になると、ドラゴン種にスノール種を交配し、ホーマー種を作り出していたし、後にベルギーとなる辺りでは、オウル種、タルビット種、キュミレット種を交雑して、スミテル種などを作り出しておった。
とすれば、絵図に描かれておった鳩小屋にいたのは、イギリス系のホーマー種か、ベルギー系のスミテル種であったかも知れぬ。とにかく、この絵図が日本における、通信鳩の最古の資料じゃろう。
元禄時代になると、中国から南京鳩が輸入されておる。出所は「和漢三才図会」じゃ。じゃが、当時は伝書鳩飼育は禁止されておったじゃろうから、これは鑑賞鳩かも知れぬ。伝書鳩であったとしても、当時は記録に残せなかったじゃろう。
わしは、この南京鳩は伝書鳩ではないと考えておるぞ。
やはり、徳川幕府は伝書鳩の飼育には、神経質になっておったように思う。それは、防御手段である「鷹狩り」を厳しく制限しておったという事実があるからじゃ。徳川家康は、皇家などの謀叛を抑えるべく「禁中公家諸法度」を作成したが、これは「東鑑(あずまかがみ)」を基礎にしたというぞ。
「東鑑」は鎌倉時代の史書であるが、一七か条からなる同法度に「天子諸芸のこと、第一御学問なり」の項目が盛り込まれ、「公家は鷹狩りのようなことをして、武家の真似ごとをしてはならない」という意味のことが述べられておるのじゃ。
おっと、今回はここまでのようじゃ。では、この続きは、次回