連載3-35、日本鳩レース界の歴史
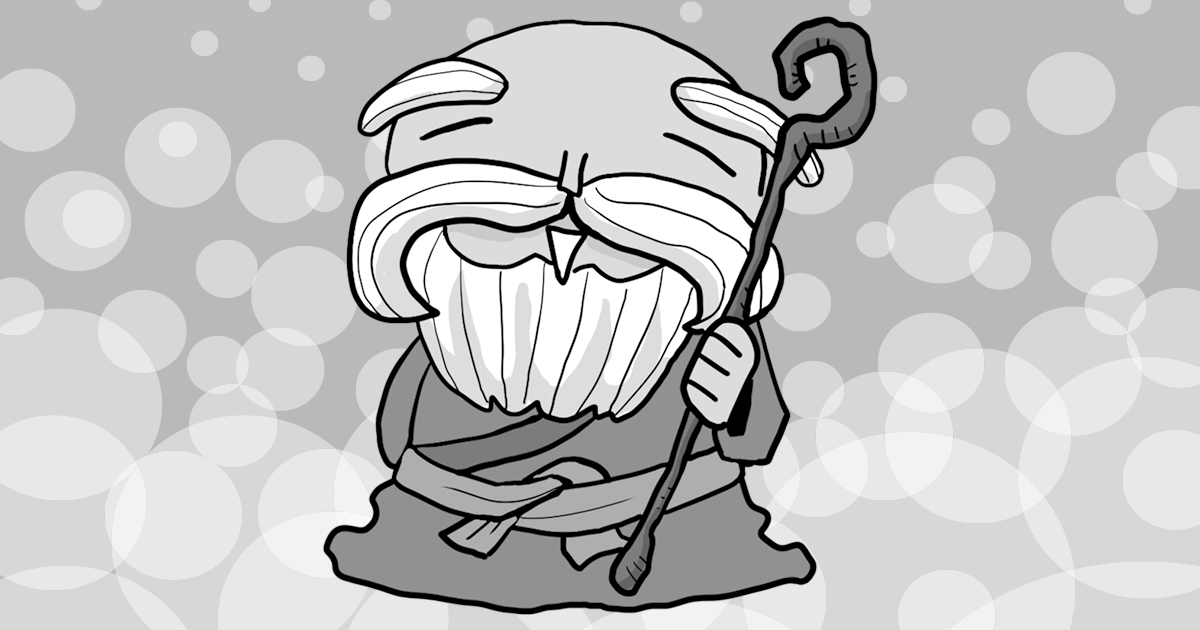
国内への渡来 その十九
前回の相模屋事件に次いで、文政年間(一八二〇年頃)には、大坂の豪商・播磨屋が大阪城代の知遇を得て「商事の通信に用いるだけ…」との条件で、鳩の使用を許可されておるが、この事実は、藩当局や大名などが、鳩の効用を十分に承知しておったという証明でもあるのう。
またこの事実は、この頃から特別な権利として、一部の限られた者には、鳩の飼育許可を与え始めていたことも伺えるぞ。
現在の江戸時代を背景としたテレビの時代劇においても、代官所や奉行所などのいわゆる体制側が鳩を利用しておったり、逆にアウトロー側が鳩を利用して体制側の裏をかいたりするストーリーを見ることがあったが、それも事実として十分に考えられることじゃろう。
実は、嘉永年間(一八五〇年頃)にも、相模屋事件と似たような事件があるのじゃ。大阪・堺の商人が、米騒動の折、ハト通信により、暴利を得ておったらしい。これも発覚早々、奉行所から使用禁止が申し渡されておる。
とにもかくにも、日本ではハト通信は為政者たちに、極度に恐れられておったようじゃ。当時は、ハト通信ほど便利なものはない。ないだけに恐れられ、それを隠密やら密偵やら忍者やら飛脚やらがカバーしておった。「切支丹の法」というような口実も作られ、武士道からは受け入れがたいという観念を与えておった。もちろん、平民による飼育などはもってのほか。厳重に禁止しておったわけじゃ。
これは、戦国時代からどんどん輸入され、やがては国内でも製造された鉄砲や短筒の例とよく似ておる。幕末まで武士たちは飛び道具の所持を忌み嫌っておったことを考えれば、わかるじゃろう。
このあたりが、ハト通信の先進国であったヨーロッパ各国と我が国の相違点というところじゃなぁ。
ヨーロッパに目を向けると、一七九一年(日本は寛政三年)のフランスでは、フランス革命が起きておる。マリー・アントワネット(一七九三年に刑死)は、タンブル城に監禁された時、あらかじめ訓練しておった鳩を使い、評定官と信書の往復をしていたという。すなわち、ハトによる往復通信の方法まで編み出されておったのじゃ。
また、一八一五年にイギリスの銀行家・ロスチャイルドが相模屋又市と同じようなことを行っておる。ナポレオンの破った連合軍の勝利をハト通信でイギリスに知らせ、数日前に自分の経営する銀行に伝えて、莫大な富を得たのじゃ。
これ以来、伝書鳩は投機業者の注目の的となり、ヨーロッパ各地で貴重な商品として取引されていく。その結果、伝書鳩の一層の改良へと繋がっていったわけじゃ。
おっと、頁がなくなってきたわい。では次回、この続きを語るとするかのう…。
(この稿、続く)